| この色即是空(しきそくぜくう)、空即是色(くうそくぜしき)という言葉は、『般若心経』というお経の中にあります。そのお経の前半に色即是空、空即是色と出てくるんです。では、色即是空、空即是色とはどういう事かと言いますと、色はそのまま空であるし、空はそのまま色であると書いてあるんですが、訳の分からない事なんです。しかし、一番大切な事なので、今からその説明をいたします。 まず、色を説明いたします。ここに笹の葉を取って参りました。この笹の葉は何色に見えますかという質問をします。何の色に見えますか、緑色ですね。笹の葉は緑なんです。緑という色が出て参りました。 でもね、もう一枚私が持ってきたとします。新緑の山から笹の葉を持って参りましたと、先程の緑の葉と並べます。何色ですか、と言いますと黄緑になります。 これは新緑の笹なんですよと言ったら、じゃぁ黄緑ですねということになる。そうすると、色というのは変化していくんです。これは緑ですねと言って、新緑のと付けると黄緑になっちゃう。でも、同じ緑のはずなんです。 こういうふうに色は自分勝手な判断が理屈で勝手に変化していくんです。だから、勝手な自分の判断を押し付けちゃう、つまり差別の始まりになっちゃうんです。 もう一つ質問いたします。 「この棒(A)は長いですか、短いですか」、「短い」。 有り難うございます。近所の保育園の子供たちば泉龍寺で月に一回、座禅会をするんですが、その子供たちはこの棒は長いか短いかを問いますと、子供たちは素直です。すぐに元気良く、 「短い」 と言います。 「本当だな」 また、又、元気良く、 「短い」 「よし」 と、そこで後からより短い棒(B)を出して並べ、 「この棒は長いですか、短いですか」 と、先程の短い棒(A)を持って聞きますと、今度は短かった棒(A)は長くなっちゃいましたね。同じ事を、棒を短くして行います。これは短い棒(B)。この棒(B)は長いですか、短いですか。と、今度は後からより短い棒(C)を出して比べてやりますと、またまた短い棒(B)は長くなってしまいました。いじわるな問題なんですが、この棒(A)は確かに長い棒です。でも、今度は机の下から、より特大の棒(D)を出してこの棒(A)と比べ合わせれば、棒(A)は短い。 つまり、この最初に出た棒は長くも短くもない棒で、空ですよと言うんです。これが空なんです。(図を参照してください クリックで拡大します) 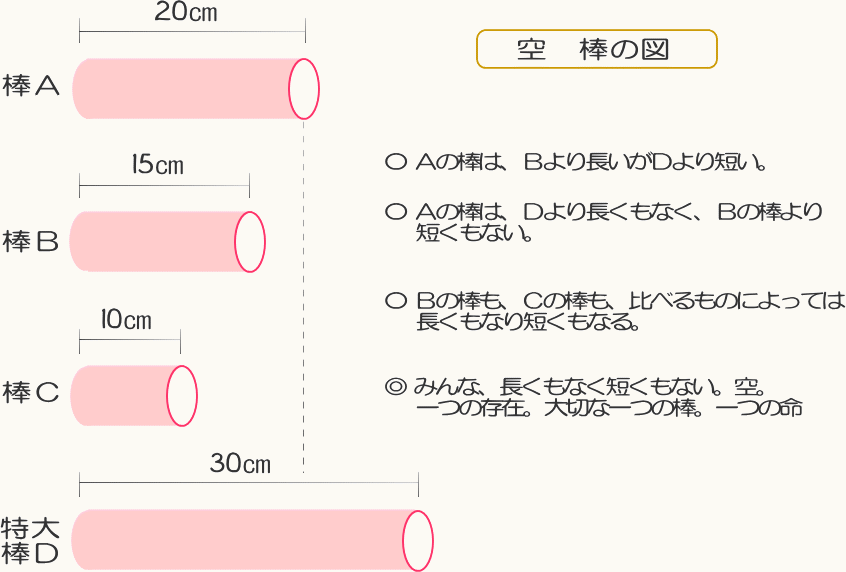 比べ合いをして赤だ、緑だ、黄色だと言って勝手な判断を押し付けている時はシキだ、色だ、シキだ。この棒は長いか短いかという範疇(はんちゅう)にある時はシキだが、長くも短くもない一個の棒だと思えた時は、空なんです。一個の存在なんです。 一個の空なんです。どの長さの棒でもね。人の事もそうやって言いますでしょう。比較して「あの人は一寸な」と。 私もよく言われます。 「あの和尚さんは、本当に説教が長い」 とか、 「塔婆の字が下手くそだ」 と、檀家さんのお宅にご法事の塔婆を書いて持って行きますと、塔婆をしげしげと見ながら、 「和尚さん、もっといい字を書きないや」 「すいません、勉強しますから」 作り笑顔して、 「どうも、どうも」 とか言って家に帰りますが、帰って明日の塔婆を書く時に、出て来るんですね。その時の思いが・・・・。「人の前で、あんなに言わなくても良いのに」とか、「私だってプライドというものが、あっ、間違えた」。他の事を考えて、字を間違えてしまう。 今はお寺に塔婆がありますが、次の塔婆を持って来まして、そしてまた次の塔婆を書いている時に、又、出て来る。「くそっ、あっ間違えた」。多い時には四本か五本くらい、間違えることがあるんです。人間って何回も間違いを繰り返しますと、思考能力が無くなるんですね。 「どうして、こんな人間にうまれたんだろうか」とか、「なんで和尚さんみたいな仕事をしなきゃいけないんだろう」とか、考えるんです。皆さんもありますでしょう。他人から悪口が聞こえた時なんか。夜、寝る前に悪口を思い出し、その人の顔を浮かべて、「あの人に、こう言われたら、今度はこう言ってやろう。こう言ったらああいうふうに言われるからああいうふうに・・・・。こう言ったら、ああいうふうに」 次第に心臓がドキドキしてくる。気分も悪くなる。そうしていると、ボーン、ボーン、ボーン。 「あっ、三時だっ、寝なくちゃいけない」、あれといっしょです。 一人で勝手に色の世界に入って、勝手に自分を苦しめて、自分で悩みをつくって、自分で悩みの中に、どんどん入っているのです。 |
 |
| このページを閉じる |